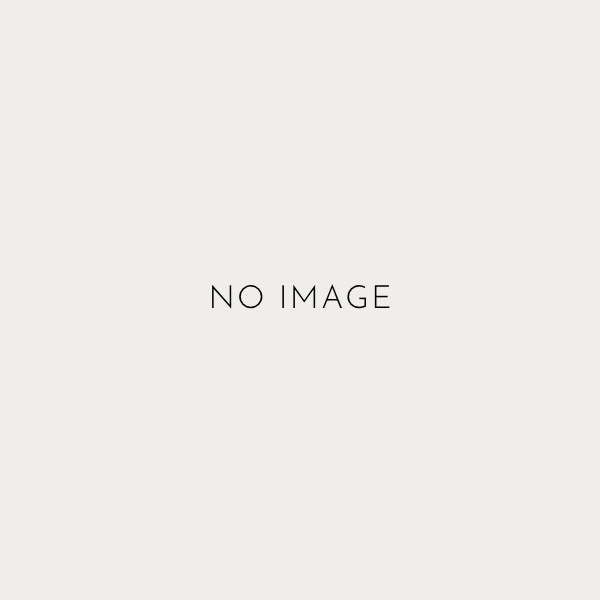1-アジアのなかの日本人
1942年、日本画家の杉山寧は中国・大同の雲岡石窟を訪れ、当地の石仏を描きました。しかし彼は、どんな仏像でも描いたわけではありません。杉山がモデルに選んだのは、優しく微笑む仏像。当時の日本では、“インド、中国の仏像や、日本の飛鳥時代の仏像は、古代ギリシャ彫刻の影響を受けている”という学説が、「アルカイック・スマイル」という言葉とともに流行していました。こうしたなかで杉山は、自分たちの源流である大陸文化への憧れと敬意を込め、数ある石仏のなかから、微笑みをたたえる仏像を選びぬいたのでしょう。彼の描く仏は、いかめしい「仏頂面」から程遠く、観る者を大きな心で包み込んでくれる慈愛に満ちています。
一方、近代の中国は、西洋のドレスと「西洋が求める中国イメージ」を合体させ、「チャイナドレス」を生み出しました。西洋が自分たちに求めるイメージを逆手にとって、新しい服飾文化をつくったのです。日本の画家たちは、こうした中国の奥深さを理解したうえで、チャイナドレスをまとった女性を描きました。彼女たちが口元に漏らす微かな笑みは、何を意味しているのでしょうか。
西洋とアジアの関係、そしてアジアと日本の関係は、作家たちがアジアへ目を向ける大きなきっかけとなったのでした。
2-大昔の器物がモダンに生まれ変わる
近代の発掘によって出土したアジアの古美術品や雑器は、日本の作家たちに大きなショックを与えました。そのフォルムや模様、絵柄は、日本の工芸の伝統からかけ離れており、作家たちに「新たな美」を教えてくれたのです。
例えばその一つに青銅器があります。青銅器は、古代中国では調理器や祭器として使用されましたが、日本の作家たちはその使い勝手以上に、フォルムや模様の面白さに惹かれました。香取秀眞の《鳩香炉》 は、古代中国の鳥型祭器からインスパイアされたものでしょう。翼の渦巻き模様やふっくらした胸が古代の鳥を思わせる一方で、愛嬌ある表情とつややかな質感、こちらに歩いてきそうな大きな足が、ユニークかつ現代的な魅力を醸し出しています。
本展ではその他にも、様々な作家たちの作品が数多く並びます。河井寛次郎は、李朝の白磁に描かれた即興性ある絵柄に心打たれ、石黒宗麿は、唐三彩において自然に流れ落ちる釉薬の美しさに魅了されました。新しい陶器づくりを志す彼らは、古美術がもっている即興性や自然性をあえて意識的につくりだすことで、自分たちの作品を完成させていったのでした。
3-現代の作家がアジアを見るとき
展覧会の最後を飾るのは、3名の現代作家による、アジアをイメージした作品です。
画家の岡村桂三郎は、古代青銅器の地紋から着想を得て、伝説上の霊獣を描きます。彼の霊獣がもつ複数の「目」は、鑑賞者のみならず、日本とアジアの行く末を見つめているのかもしれません。
漆芸家の田中信行は、かつてオリジナリティを求め、漆芸の「伝統」や「常識」を覆すオブジェをつくり続けてきました。しかし近年、彼は自身のもつ漆の技術が、日本や東洋と切っても切れないものであると気づきます。その変遷を経たうえでの今回の作品は、田中にとってもアジアを大きく意識したものとなりました。
ファッションデザイナーの山縣良和は、70年代の日米繊維交渉をテーマにデザインします。当時の西洋とアジアの経済的対立構造を視野に入れたこの作品は、現在にも尾を引く微妙な力関係をも想起させるものでしょう。