アジアのイメージ―日本美術の「東洋憧憬」展 館長インタビュー樋田豊次郎(東京都庭園美術館 館長)

「アジアのイメージ:日本美術の<東洋憧憬>」展についてのインタビュー
樋田豊次郎館長
2019年10月12日より開催される「アジアのイメージ:日本美術の<東洋憧憬>」展。展覧会企画者は、当館の館長講座でもおなじみの樋田豊次郎館長です。展覧会へのアプローチから視点まで、インタビューを行いました。聞き手は、織言堂の杉山詩織さんです。
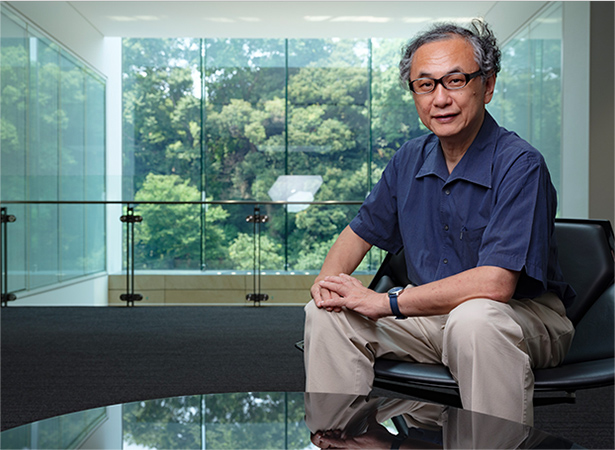
「アジアのイメージ:日本美術の<東洋憧憬>」展についてのインタビュー
樋田豊次郎館長
2019年10月12日より開催される「アジアのイメージ:日本美術の<東洋憧憬>」展。展覧会企画者は、当館の館長講座でもおなじみの樋田豊次郎館長です。展覧会へのアプローチから視点まで、インタビューを行いました。聞き手は、織言堂の杉山詩織さんです。
―― 今回の展覧会は、1910〜60年頃までの絵画、工芸品、そして現代作家の新作を通じて、アジアと日本の関係を考えるものとなっています。なぜ今、このような展覧会を開催しようとお考えになったのでしょうか。
樋田
現在、日本の美術界でアジアを見直そうだとか、アジアから何かを汲み取ろうとする「大きなうねり」があるわけではありません。しかし、それはそれとして、ベルリンの壁が崩壊して以来、東西の対立構造が変化して、いろいろなものが変わっているのです。
芸術の分野でも、以前は東西の対立軸のなかで「自分の美術とは何か」を考えていれば済みました。日本の作家であれば、パリやニューヨークのものを学んで、それを上手に咀嚼し、制作すればよかったのです。でもそうした構造は変わってしまいました。西欧やアメリカは「先生」ではなくなり、また逆に、それらの国々を批判していれば良いという「反面教師」でもなくなりました。だから日本は、自分たちで自らの美術を考えなければならなくなったという構造があるのです。
でもそうしたとき、私たちは実際にはどうしたらよいかわかりません。そこでひとつの考え方として、自分の足元、つまりアジアを見るという手立てがあると私は思うのです。逆にいえば、アジアを抜きにして「パリやニューヨークはこうだ」といっていても、地に足がついた美術は日本から生まれてこないと思うのです。だから今回の展覧会のような、アジアへのまなざしを内包する美術は、避けて通れないだろうと思っています。このような思いがベースにあるのです。
そしてその次の段階として、「じゃあ、具体的にアジアをどう見たらよいのか」という問題が出てきます。たとえば「アジアの美術は西洋に比べて遅れている」だとか、西洋の「オリエンタリズム」のように「アジアとはこういうものだ」という勝手なイメージの押し付けをしても、それは意味のあることとは思えません。「今、アジアを見る」といったところで、オリエンタリズムを焼き直しているだけでは、本質的なものは見えてきません。だとすれば、どのような目でアジアを見ればよいのでしょうか。
そこで今回は、過去のある時期における日本の美術家たちを、ひとつの手がかりにしました。1910〜60年頃までの日本では、アジアの古典美術に〈影響〉を受けた作品がたくさん生まれています。それらの作品が制作された〈動機〉や、ひるがえって、そうした作品が日本文化に与えた〈効果〉を見ることが、「今、アジアをどう見るか」という問題を考えるきっかけになると思ったのです。今回の展覧会の裏には、そのような三層構造の思いがあります。
―― そもそも1910〜60年頃までは、作家たちにとってどのような時代だったのでしょうか。また、作家たちに影響を与えたアジアの美術品とは、どのようなものですか。
樋田
作家に影響を与えた要素のひとつに、アジアの古典美術がありました。それらは今では博物館に行ったり本を開けば見られますが、戦前は簡単に見ることができないものでした。当時は博物館といっても、いくらも展示されていないわけですし、(旧)華族は自分たちの所蔵品を一般公開していない時代です。だから普通の画家や工芸家たちは、見るチャンスがありませんでした。
ところがそのうち、大陸で鉄道の敷設、工事、河川氾濫など、さまざまなことがあり、発掘作業が行われて、たくさんの考古遺品が出てきました。それから、日本人が大陸へ旅行して、現地のものに触れたということもあります。そして、それらが日本に持ち込まれ、また従来から中国や朝鮮半島で伝世してきた古美術も、日本に輸入されてきたのです。考古遺物や古美術を見た絵描きや工芸家たちは衝撃を受けました。そして、それらをアジアの古典美術なのだと認識しました。
彼らにとってアジアの古典美術とは、新しいイメージを与えてくれる源泉となりました。どんな分野の美術にも、日本のなかで歴史的に出来上がってきた伝統や格式、形式がありますが、それを一旦捨てさせるものが、アジアの古典美術にはあったのです。それを実感することが、当時における「アジアを見る」ということだったのですね。
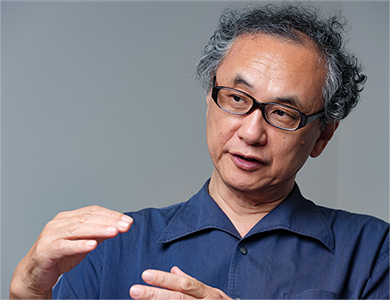
―― では今回の展示作品の作家たちは、何か自分の殻を突き破りたいという思いがあったのでしょうか。
樋田
あったと思います。だからそれぞれの作品に、どのような殻を破ったかという話が、一つひとつあると思うのです。今回は、それらをなるべくたくさんご紹介したいと思っています。
新しい価値観から生まれた作品たち
―― さまざまな作家たちが、古典美術に驚き、自分の新たな作品をつくっていったとのことですが、安井曾太郎の《薔薇》は、この時代にとって新しいものを描いているということでしょうか。

樋田
この絵は、全体は西洋から学んだ静物画です。ですが、そこに白い陶器を描き込んでいます。白磁の上に黒い釉薬で描いているこの花瓶は、磁州窯の壺です。磁州窯は、当時発掘されて存在がわかってきた古美術でした。だから物は古くても、安井にとっては初めて知ったものなのですよ。とてもインパクトがあり、これはすごいやと思って描いたのです。
百科事典によれば、バラの原産地は小アジア(おおむねトルコ)だそうですが、この絵の場合、西洋から伝わってきたバラを主題にした静物画のなかに、花瓶によって東洋を挿入しているということですね。しかも、何世代も前から知っている東洋の陶磁器ではなく、ごく最近に知った東洋の考古遺物を選んだわけです。それが面白いから描き込んだのでしょう。
―― 「新しい古典」を絵で表現したのですね。
出土品つながりでいうと、この「鼎(かなえ)」というものは何に使うものですか。
樋田
鼎は、もともと肉か何かを煮込む鍋ですね。《饕餮文鼎(とうてつもんかなえ)》は商の時代(紀元前17〜11世紀)のものです。

―― 足が3本という変わった形をしていますね。
樋田
一般論ですが、3本のほうが4本より安定しているのです。火を焚いてその上で調理する鍋の足なので、この形が有効だったのでしょうね。ただ、祭器の要素もあります。神様に何かを捧げるときに、これで煮炊きしたのでしょう。とくに、饕餮文は魔除けの文様でしたから。

―― 一方、高村豊周の作品《鼎》、これは《鼎による花入れ》とも呼ばれていて、用途が花入に変わり、フォルムがすっきりしています。それに3枚の葉っぱのようなものが描かれています。
樋田
新しい作品をつくるにあたり、出土品のデザインをそのまま持ってきてしまうと「写し」になってしまうでしょう。近代化した作品にするために、饕餮文を幾何学文に変更したのです。
鼎は3本足という完成されたフォルムでしょう。しかも古代青銅器です。つまり完成された古典です。それをもとに自分の作品をつくるということは、口で言うのは簡単ですが、とても大変なことですよ。
他にも岡部嶺男は《青織部縄文鼎(あおおりべじょうもんかなえ)》や《翠青瓷鼎(みどりせいじかなえ)》において、すごく格闘していて、足を曲げたりしているけれど、古代の鼎を充分咀嚼して、ブレイクスルーしきっているかというと、まだ戦っている途中という印象があります。戦っている途中だったから、彼は縄文の叩いた感触や質感を出したり、青磁釉という、この鼎が製作された商(紀元前17-11世紀)の時代にはなかった釉薬をかけています。全然違う要素を突っ込み、なんとかブレイクスルーしようとしたのです。
古典的なフォルムや様式、造形の技法というものは、それくらい強いのですよ。簡単に壊せるものではありません。壊しても「ただ壊した」と評価されるだけでは、自分の作品とはいえません。これはものすごく格闘している作品なのです。
ちなみに岡部嶺男の《青織部縄文鼎》は、1955年の日展に出ているのですが、高村豊周の《鼎》も同じ展覧会に出品されているのです。別に2人で示し合わせたわけではないのです よ。工芸家たちがアジアというものを戦前からずっと見てきて、なんとかこれを近代的な自分の作品にしてやろうと戦ってきた結果、偶然最後に、同じ展覧会に出されたのです。



―― 同時に出されたのが面白いですね。
ちなみに高村豊周は、このシリンダー状の花瓶もすっきりしたデザインでつくっていますね。
樋田
この《青銅斜交文花瓶 》のフォルムは、外側から見ると大から小へと、同心円で繋がっているでしょう。しかも表面には、斜交文という幾何学的な文様があしらわれています。これは発想としてはアール・デコです。
ここまで西洋的な幾何形態(アール・デコ)を志向しながらも、雷文(《鈎連雷文瓿》)がもっている東洋的な地文様も活かしている。それが高村豊周の才能だったと思います。
―― なるほど。
この壺は、夜空を鳥の群れが飛び交っているみたいですね。(《黒秞褐斑鳥文壺》)


樋田
《黒釉褐斑双耳瓶(こくゆうかつはんそうじへい)》や《黒釉銹花草花文瓶(こくゆうしゅうかそうかもんへい)》を見てください。「黒釉褐彩」は、日本語で説明しているように読めてしまうのですが、実は中国語なのですよ。13〜14世紀のアジアで、黒い釉薬に褐色のまだらな文様や図柄を入れ込むという技法が、ひとつの様式として成立していたのです。石黒宗磨はそれを自分で読み解き、このような文様にしてみようと試みたのです。描かれているのは鷓鴣(しゃこ)という鳥です。
―― 黒一色の地色を活かしたのですね。
この籠はどのような方法で使うのでしょうか。(《提梁花籃》、《花籃》)


樋田
主に明の時代らしいのですが、中国の文人たちは、普段の生活で使われていた雑器の籐籠を、煎茶の場で花生けとして使ったそうです。つまり日用雑器だったものを芸術品に変えてしまったわけですね。
その後、近代日本で煎茶が流行したときに、このような籐籠(《提梁花籃》)が入ってきたのですが、それを知った飯塚琅玕齋という人が発想を変えて、新しい竹籠をつくったのです。明代の文人たちが雑器である籐籠を芸術品にしたのと同じように、日本の雑器である竹籠を芸術、オブジェにしたのですね。(《花籃》)
琅玕齋のほうは、編むときの法則性を乱しているでしょう。中国の籐籠は雑器であっても、端正で、法則性のある編み方を守っていました。しかし琅玕齋は違いました。アジアにおける「雑器を芸術にする」という部分は受け入れたけれど、「編む」という行為を思い切り破壊してみて、どのようなフォルムが出てくるのかを試したわけです。そこに彼の「天才」があったのです。


―― 「器」でいうならば、こちらの白磁はどのような意味があるのでしょうか。(《青花草花文面取壺》、 《鉄砂草花文壺》)
樋田
これは李朝のものです。李朝の白磁では、模様の染付において、即興性が非常に重要です。いかにも端正に描きこんだというよりは、思いつきで草花をシュシュッと描いているようでしょう。それから染付だけではなくて、鉄砂という茶色っぽいものもあります。色を出す絵の具の種類が違っていても、描き方としては雑器に描いたようですよね。そのようなものが李朝では好まれたのです。
こうした白磁の文様は、かならずしも即興ではないのですが、あたかも即興であるかのように描かれます。端正な文様や、堅苦しい形式ばった左右対称や、構築的な図柄を嫌ったわけです。河井寛次郎はそれを汲み取って、自分のものにしていったのですね。彼は近代の陶芸家なので、近代の感覚のなかでそれを再現しています。
―― どのあたりが近代的なのですか。


樋田
即興性があるように見える李朝のものを、絵画的に表現したところでしょうね。野草を見ているような李朝のものは、どこまでいっても模様のように描いています。かたや河井は、一見自由だけれど、きちんと絵画的に組み立て直したのです。
―― ところで、自分のなかに根付いてしまっている「伝統」や「形式」を壊すために、他の国の形式を真似るというのは面白いですね。
樋田
その言い方はちょっと意地悪ですよ。
真似ているのではないのです。作家たちは、やっぱりショックを受けたのだと思います。いかに自分が形式的につくっていたのか、気付かされてしまったのです。また、アジアの古典美術なら何でも良かったわけではないのです。みんなそれぞれ、ちゃんと重要な部分を選んでいるのです。「李朝」の「白磁」の「染付」だとかね。それぞれの国や時代の、ある部分を選んでいます。そこに自由や独創性があるなと思ったものを手引きとして、自分がこれまでもっていた価値観を壊していったということです。
たとえば鹿が飛び跳ねていく文様(《草花鳥獣文小手箱》)だって、もともとはスキタイやササン朝ペルシャで生まれた狩猟文なのです。王侯貴族が狩りをするとき、動物たちが逃げていく様子を、織物でパターン化した模様がありました。そしてそれが漢時代の壺(《緑釉狩猟文壺》)にまで伝播しているのですが、松田権六はそれを見て面白いと思ったのです。松田は、狩猟文をそのままステレオタイプとして写しているのではなくて、あたかも動物たちが楽しく走り回っているかのように、解釈し直したわけです。だからこれのタイトルは「狩猟文」ではなく、「走獣文」なのですよ。
―― 「走獣文」という言い方は、日本独自のものなのですか。


樋田
もしかしたら中国にもあるかもしれませんが、少なくとも、日本人がこれを再現したときの意識は「狩猟文」ではなかったのです。とくに増田三男の作品などは、《金銀彩壺 山背》というタイトルにしています。「山背」とは、木枯らしです。意識が変化しているのがわかるでしょう。寒い風が山の上から吹いてくるから動物たちが走り去っていくような作品です。けっして、弓矢で射殺されないように逃げているのではないのです。
それから「唐三彩」って聞いたことがあるでしょう。ラクダや女官や人物の俑(よう 中国で用いられた陶器製の副葬品)が有名ですが、これ(《三彩壺》)も唐三彩です。「唐三彩」というくらいだから、三色(黄色、緑、褐色)の釉薬を掛けるわけです。それに、藍色が加わることもあります。
これらは原理的にいうと、三種類の釉薬を掛けて、焼成しているだけです。焼いている途中で釉が流れて、自然に斑(まだら)な文様になっていくように、釉薬を掛けています。とはいえ、まったくデタラメに掛けているわけではないのです。そこで、唐三彩を見た日本の石黒宗磨は、釉薬をあたかも自然に流し掛けたような、斑文様の面白さに目をつけました。
彼は主として藍だけを使っていますが、こちら(《藍彩壺》)のように、新しい文様に再構築したのです。もとは唐三彩の釉薬の自然文様でした。それを意識的に新しい装飾芸術にしたのです。
当時、普通の人は唐三彩なんて見たことがありませんでした。お墓の副葬品でしたからね。やはりこれも近代に発掘されて日本に入ってきたものです。
たとえばあなたが、ラクダや女官の唐三彩を見て驚いたところで、「さあこれをイメージソースにして自分の作品をつくってください」と言われたら、なかなか大変だと思いますよ。あれだけ完成されたフォルムや色調を完全に咀嚼して、自分の作品にしていくことができた石黒は、天才だと思います。



―― 作家たちは出土した古典美術を見たとき、フォルムや模様、技法に感動したということですが、仮にこれが中国などではなく、アフリカや南米のような、アジアではない地域のものだったとしても、同じフォルムであれば、同様に感動したのでしょうか。
樋田
そこは難しいところです。もともと日本は歴史的に、アジアへの憧れがあったから、このようなことが起こったのだと思います。もともと日本人はアフリカの土器に対する憧れはありませんから。レヴィ=ストロースが先住民の土器を研究したり、日本の川田順造もアフリカの土器を研究しています。しかしだからといって、アフリカの土器を見て、ほとんどの日本の芸術家は自分の進むべき方向だとまでは思いませんでした(小川待子のような例外はありましたが……)。日本人はやはりアジアに対しては、基本的に憧れがあるのですよ。
―― ここまでのお話を伺っていると、アジアへの憧れと近代的な感覚が交差する作品が多いですね。
《双魚衝立》はモダンでかわいらしい感じのデザインです。庭園美術館の本館に似合いそうですが、中央に魚がついています。
樋田
魚は卵をたくさん産むので、もともとアジアでは吉祥文なのです。子孫繁栄のシンボルなので、魚文様は、あちこちのデザインによく出てきます。
これはストーブガードです。暖炉を使わない夏に、暖炉の前に置く衝立です。作者の北原千鹿という人は、西洋風の生活文化を昭和初期に目指しました。このストーブガードは、全体的にいえば西洋デザインそのものですが、その中心の部分は、東洋で吉祥紋として愛好されてきた双魚文なのです。自分を育ててきた文化の根っこをどこかに保存しておかないと、ただのモノマネ的な西洋生活になってしまうでしょう。何か必要だったのです。私はそれが面白いと思うのです。
それから、この魚自体も面白いのです。東洋的な魚文からいえば、互いに追いかけているような構図になるので(《青磁貼花魚文盤》)、本当は、ここは逆向きにならなければいけません。でもこのストーブガードではそのような意識がないので、同じ向きで並べてしまっているのです。
他にも、双魚文の魚は二匹が同じサイズをしていますが、石黒宗磨は《刷毛目双魚文平鉢》において大小の差をつけて、あたかも皿の上に焼き魚がのっているかのようにしています。魚文自体は受け継いでも、解釈を変えてしまったのです。そこに面白さがあります。



―― 文様がかつてもっていた意味は置いておいて、魚の形自体を楽しんだということですね。
樋田
そうです。だからこの作品を展示するコーナーの名称は「文様から装飾芸術へ」にしています。
吉祥紋に限らず、アジアには松竹梅や花鳥など、器物の表面を覆ってきたさまざまな文様がありました。たいていは縁起のよいものです。それらは当初、子孫繁栄など、生活から生まれてくる意味が込められていました。
しかし北原たちは、その伝統的生活から発生していた意味をすべて剥ぎ取っています。剥ぎ取ることによって、ストーブガードの中心核になれたのです。もともとの生活上の意味をとっぱらったことは、文様を近代的な装飾芸術に生まれ変わらせることであり、伝統的な考え方を変えていったことでもあると思うのです。
―― アジアへの憧れがあれば、アジア的思想を受け継ぐかと思いきや、そうでもないのですね。
樋田
それが近代であるともいえますが、やはりこれらの作品をつくっている人たちの才能だと思うのです。才能のない人がやれば、昔の意味を引きずってしまうと思います。そこを思い切って断ち切り、近代芸術にしていく。先ほどの鼎や、狩猟文を走獣文に置き換えてしまう話も、すべてそうだと思います。
アジアのなかの私たち
―― 展示の見どころの一つに、杉山寧の描く仏像があります。作者はどのような視点でアジアを見ていたのでしょうか。(《雲崗5窟 如来像》)
樋田
「アルカイックスマイル」という言葉がありますね。あれはドイツやフランスの人たちが、ギリシャの古代彫刻を見ていいだしたことなのですが、和辻哲郎、亀井勝一郎、会津八一たちは、それを飛鳥時代の仏像や、中宮寺の半跏思惟像など、日本の微笑んでいる仏像にも当てはめたのです。アルカイックスマイルを「古拙の微笑」と訳し、それを日本の古代美術に使うことで、芸術の道がギリシャから東へ繋がり、最後に日本があるのだというロマンをつくったわけです。
これが100パーセント事実かどうかは難しいところです。たしかにヘレニズム文化は、西から少しずつインドまで来ていますからね。だけれど、インドからどうやって中国、日本へきたかは、学術というよりも、すごく感覚的なイメージで語られています。西洋から伝わってきた美が、最後には中宮寺の仏像のように、すばらしいものをつくったのだという「共同幻想」を、当時の日本人がとても喜んだのです。
そうした言説のなかにいた杉山寧は、中国の大同へ行きました。大同の雲岡石窟には大きなものから小さなものまで、何千体という石像があります。制作された時代も多少幅があります。だけど基本的に、ここの仏像はリアルで即物的であり、実在の人間みたいです。そのようななかから、杉山はわざわざ飛鳥仏のように微笑んでいる仏像を見抜いて、絵のモデルに選んだのですね。当時の日本人が愛し、流行させた「アルカイックスマイル」を追う目で、雲岡石仏を見ているのです。
杉山によるアジアへのまなざしを考えることは、なかなか難しいことでもあります。アジアに対して、自分たちに都合の良いものを見ているのではないか。場合によっては、アジアに中宮寺的な美を押し付けているのではないか、とも言えるわけですね。バイアスがあったかどうかは、これから少しずつ調べていかなければならないと思います。


―― では、こちらの絵に描かれているチャイナドレスの女性たちに対しても、作者は自分たちのアジアイメージを押し付けていた可能性があるということでしょうか。(安井曾太郎《金蓉》、藤島武二《匂い》)
樋田
これは、むしろ正反対な事例です。そもそもチャイナドレスというものは、女性美を誇張させる衣装ではありませんでした。
岡田謙三が中国女性の普段着を描いているでしょう(《満人の家族》)。これは満州に行った彼が描いたものです。詰襟っぽくなってはいますが、ワンピースではありませんよね。
一方で安井曾太郎の《金蓉》はいわゆるチャイナドレスです。このドレスは、中国の人たちが西洋人のオリエンタリズムを逆手にとって「どうだ、こうしたらあなたたちの夢が本当に叶うだろう」と発明したものなのです。中国は、西洋人の抱きたがっている中国イメージを受け止めたわけですが、その状況を日本の画家たちは、新しいアジアのなかの息吹として記録していったのです。つまり中国の文脈をわかったうえで、あえてチャイナドレスを描いているのです。中国に行って見てくれば、こんな服を着て労働している人はいないとわかるのですからね。


―― 展覧会の第Ⅲ部では、3名の現代作家が新作を発表されます。これらの作品には、アジアへのどのような思いが込められているのでしょうか。
樋田
まず画家の岡村桂三郎さんは、古代アジアに畏敬の念をもっているように思えます。動物たちを、あたかも古代の伝説上の霊獣であるかのように描いてきたのですから。岡村さん自身のキャラクターもあると思うのですが、彼は人と対するときや作品づくりにおいて、世の中の権力関係を持ち込もうとはしません。
つぎにデザイナーの山縣良和氏さんですが、この作家は、やはりミラノやパリのコレクションといった、ファッション分野の経済的な力関係がつねに働いているところで生き抜いてきたからでしょうか、ものごとの力関係に関心があるように思われます。
今回の作品は、《Tug of War 狸の綱引き》というタイトルです。1970年代に「日米繊維交渉」というものがありました。日本が繊維をどんどん売ってくるので、アメリカが怒ったことがあったのです。そのとき「日本は繊維の輸出では譲歩し、それと引き換えに、縄を買った」と、アメリカの新聞は書いたそうです(Sell Yarn, Buy Rope)。「縄」は沖縄のことです。日本は繊維交渉では負けて、アメリカの言いなりになったが、その見返りとして沖縄を返還してもらった。沖縄の本土復帰は1972年ですよね。そこをテーマにした作品です。山縣さんはファッションを扱われるデザイナーなので、糸や縄に敏感に反応したのだと思います。また、西洋のアジアを見る目にも感応しているのでしょう。
それから最後に漆作家の田中信行さん。彼は日本漆芸の格式ある技法や伝統を大学で叩き込まれたのですが、大学を出てみると、どうも世の中、教わった通りにはなっていないなと思うようになるのです。世間全体はけっして「伝統」だけで成立しているわけではないと気づいて、そこから出ようとしました。そのため彼はオリジナルのオブジェをつくるようになり、これまでそれが評価されてきました。
しかし、かつて学んだ伝統技法というものは、やはり日本漆芸史のなかで形成されてきたものなので、その技術自体は、伝統的なものをつくることに一番向いているのです。漆は漆でも、西洋人が使う技術とは違うのです。その意味で彼は、自分がいったん切り離したはずの伝統様式の技術が、やはりどこか東洋と繋がっているのだと近年気づいたのでした。そのため今回は、東洋の原点となるようなフォルムを、自分なりにもう一度見てみようという意識で制作しています。新作は三者三様になりました。
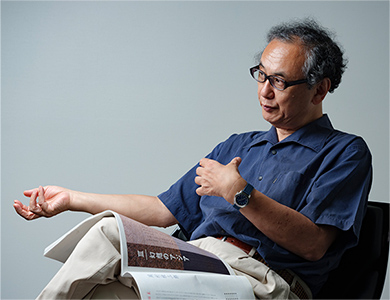
―― 新作を拝見するのも楽しみです。
最後に、この展覧会を開いた結果、どんなことが起こったら嬉しいと思われますか。
樋田
やはり今回の展覧会では、作家たちがアジアに憧れをもっていたということが、とても重要であり、本質だと思うのです。憧れをもとに、日本の美術家たちは、日本という国の芸術的フレームワークから自らを開放していきました。
ですから私は、私が意図しようとしまいと、展覧会のお客さんのなかから、つぎのような人が現れることを期待したいのです。「作家たちは、アジアの古典を自分なりに表現していて素晴らしいな」と言ってくれるお客さんの出現も嬉しいのですが、それを超えて、「日本人って案外こういう形で、ナショナリズムや帝国主義、『日本はスゴイ』といった気持ちを、乗り越えてきたんじゃないかな」と気づいてくれる人の登場です。つまり、アジアを見ることで、自分のもっている「日本」という殻を破ることを本能的に感じ取ってくれる人。そう感じる人が増えるといいなと思います。
この展覧会によって、「今が日本の文化にたいして内省的になるチャンスだ」と気づいてくれる人が出てきたら嬉しいですね。

―― ありがとうございました。
東京都庭園美術館館長 樋田豊次郎
1950年生まれ。1979年より東京国立近代美術館工芸館に勤務。2007年に秋田公立美術大学理事長及び学長に就き、16年から東京都庭園美術館館長。日本ならではの造形芸術として「工芸」の再評価を試みてきた。主な展覧会は「ヨーロッパ工芸新世紀」(1997)、「工芸の領分」(1994)等。著書は『明治の輸出工芸図案-起立工商会社工芸下図集』(1987)、『工芸の領分-工芸には生活感情が封印されている』(2006)他多数

