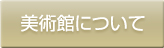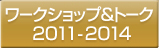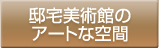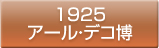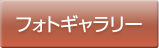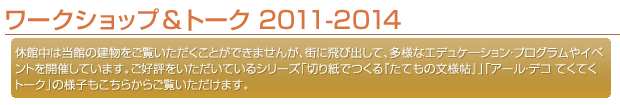
Vol.1 東京都庭園美術館(1)
「密度が高くて目が離せない!アール・デコ日仏エンドレスバトル!」
- 場所:東京都庭園美術館
- 日時:2011年10月18日(火)18:00~20:00
- 講師:米山勇(江戸東京博物館 都市歴史研究室)
2011年10月18日(火)と10月25日(火)東京都庭園美術館では、建築の専門家を講師に迎え、当館の建築について熱く語っていただく「たてものトーク」を開催しました。第1回目、第2回目の「アール・デコ てくてくトーク」では、その時の様子をレポートします。
10月18日(火)の講師は、江戸東京博物館 都市歴史研究室の米山勇氏です。米山氏は建築史家として、また今流行の「けんちく体操」の考案者としても知られています。トークの導入として準備されたアール・デコ調の映像とともに、米山氏の熱い語りが始まります。
米山氏
「アール・デコ建築には、いつくかの特徴があります。一つ目はギリシャ・ローマをはじめとする歴史的な建築様式を積極的に取り込み、それをパロディ化して用いるというものです。」

図1: |

図2: |
東京都庭園美術館の外観はとてもシンプルで、縦長の窓の形などを見ると、アール・デコ建築というよりもむしろインターナショナルスタイルを想起させる、と米山氏は指摘します。ただし、よく見ると、建物の二階に配された半円形の出窓、正面入口の車寄せのアーチなど、様式的な要素が含まれており、そこに「ずらし」の手法を加味するところに、アール・デコ建築の特徴が現れていると言います。(図1)
さて、このようなアール・デコ建築の特徴を踏まえたところで館内に入ります。美術館の正面玄関には、アール・デコ様式を代表するガラス工芸作家ルネ・ラリックが制作したガラスレリーフ扉があります。この扉そのものが貴重な芸術作品であり保護の観点から、普段はこの扉は開放していません。しかし、今回は特別にこの扉から中に入れるようにしました。(図2)ここでさらに、米山氏は、アール・デコ建築の二つ目の特徴について言及します。
米山氏
「異質な素材を混在させるというのもアール・デコ建築の手法の一つですね。素材感の期待を裏切る、まるでマーラーの音楽のような建築ですね(笑)」

図3: |
たしかに、館内のあらゆる場所では、異素材の組み合わせがさりげなく使われています。例えば、正面玄関のラリックの扉は、ガラスと鉄が、大食堂の壁面はオレンジ色の大理石と銀色に塗られた漆喰の壁が、そして、中央階段の装飾部分も大理石とブロンズという素材が(図3)、それぞれ組み合わされています。しかし、不思議なことに部屋全体は統一感を持っており、異質な素材同士が違和感なく溶け込んでいます。米山氏はそれを「マーラーのような建築」と言うのでしょう。世紀末ウィーンで活躍したマーラーも、声楽と器楽という異なる要素を混在させた交響曲を作曲しましたが、不思議なことにその音楽はある統一感を保っています。異なる素材を組み合わせながらも空間の全体の雰囲気を壊さないという点に、アール・デコ建築とマーラーの音楽の共通点があるのかもしれません。そしてさらに、米山氏はアール・デコの三つ目の特徴について触れます。
米山氏
「一見、複雑に見えるデザインが、よく見ると単純な構成を繰り返しているというものアール・デコの大きな特徴のひとつです。アール・デコの根底にあったものは、“手抜きの美学”であったと言えるかもしれません。」

図4: |
当館の館内は、照明やラジエーターカバー、通風孔など細部までデザインされていますが、よく見ると同じデザインを使っていることがあります。1階大客室のガラスエッチング扉はその代表的な例でしょう。(図4)香水塔と大客室との間にあるその扉は、エッチングを施したガラスを鏡に貼り付け、30枚のパネルを組み合わせたものです。一見、個々のパネルのデザインは複雑なように見えますが、注意深く眺めると、3種類のデザインのパネルを、ある一定の規則に従って繰り返し使っていると分かります。複雑さを装いながら、実は単純な繰り返しを用いている、そこにデザインが規格化されていくマシンエイジ時代の美意識を反映させたアール・デコの特徴がよく出ている部分と言えます。

図5: |
過去の様式を引用し、異質な素材を混在させ、単純なデザインを繰り返す、というアール・デコの特徴を踏まえて鑑賞することで、当館が「アール・デコの館」と呼ばれる所以をより深く感じていただけたのではないかと思います。そして、米山氏が本トークのテーマとして取り上げたように、当館の基本設計を担当した宮内省内匠寮が、欧米の建築・デザインの最新の動向を取り込もうと格闘した成果が、当館のあらゆる場所に刻み込まれていることも忘れてはなりません。当館の様式を見ることは、日本におけるアール・デコ建築の受容についての考察を深める足がかりになるにちがいありません。(浜崎)