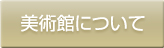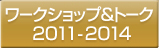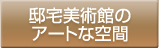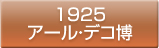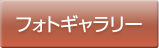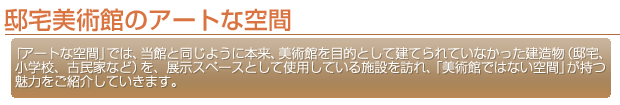
第2回 三菱一号館美術館(旧三菱一号館)

写真1:三菱一号館美術館外観 |
三菱一号館は1894年に竣工された丸の内初の洋風建築のオフィスビルです。設計は、鹿鳴館や旧岩崎邸などで知られるイギリス人建築家のジョサイア・コンドルによるもので、19世紀後半のイギリスで流行したクイーン・アン様式が用いられています。当時は、三菱合資会社の銀行部の他、貸しオフィスとしての機能もあったそうです。1968年には老朽化のため惜しくも解体されましたが、その後40年の月日を経た2010年に同じ場所に忠実に復元されました(写真1)。
背景にある現代的な丸の内パークビルディングと、まるで明治時代にタイムスリップしたかのような三菱一号館美術館が繰り広げる、現代と過去とのコントラスト…今ではすっかりオフィス街にとけこんだ姿となりました。今回は、歴史的な建物を美術館として活用する面白さや難しさ、また都市の中に存在する美術館としての工夫などを、三菱一号館美術館副室長の鬼柳求さん、主任学芸員の安井裕雄さん、広報プロモーション担当の石神森さん、酒井英恵さん、後藤夕紀子さんの5名よりうかがいました。
「Café1894の内装復元は、明治時代の一枚の写真が大きな手掛かりとなりました」
鬼柳さん
「出来る限り忠実に復元した部屋というのは、現在Café1894になっているかつての銀行営業室と歴史資料室と応接室だけになります。壁に漆喰が塗ってあるのは、その3部屋だけで、特にCafé1894のの空間については、明治時代の写真一枚が大きな手がかりとなり、ほぼ完全な形で復元出来ました。」

写真2:旧銀行営業室(明治時代) |
三菱一号館を現代によみがえらせる事が出来たのは、竣工当時の設計図、解体時に記録されたという実測図、写真や保存部材等が残されていたためです。それらの資料に基づき、当時の製法・工法を可能な限り忠実に復元したとのことです。例えば、外壁を朱色で飾るレンガは、最後に入居していたテナント会社(旧富士電機株式会社)がたった1つだけ、大切に保管していたレンガを元に、なんと当時の風合いまで再現したそうです。そして、日本全国から集められた約100名のレンガ職人が実に230万個のレンガを丁寧に積み上げこの建物は復元されました。
また、復元された3つの部屋の1つであるCafé 1894は、たった1枚の写真(写真2・5)と図面・保存部材を元に現在によみがえらせることができました。柱、天井、照明、カウンター、鉄骨回廊など、当時の様子を出来る限り忠実に復元しています。
一般的に美術館というとホワイトキューブと呼ばれる白い壁の箱型の空間を思い浮かべますが、それとは異なりクラシカルな雰囲気を味わいながら鑑賞を楽しむ事が出来るのは、明治の建物を現在によみがえらせようとした三菱地所の気概と技術力のたまものなんですね。
「ヒューマンスケールなので、展示は面白いと思います」
安井さん
「この建物は、実に個性的だと思います。世界中の新しく出来上がる美術館がホワイトキューブであるのに対して、ここは空間のプロポーションが小さくヒューマンスケールなので、展示は面白いと思います。」

写真3:展示室 |
三菱一号館美術館の空間の最も大きな特徴は、「貸しオフィス」として使われていたことです。つまり、建物の各展示室の空間が小さく、細かく区切られているため、一般的なホワイトキューブの美術館のようなニュートラルで広い展示空間を持つことができないのです。しかしながら、その特殊な空間こそが、展示室の味になっています。例えば、ヒューマンスケールゆえ室内と作品と鑑賞者の間に親密な空間がうまれ、じっくり作品と向き合うことができます。それは広い展示室では味わえない贅沢な体験であるといえます。また、全ての展示室が同じサイズではないため、小さな展示室から大きな展示室へ抜けると、ある種の解放感を得ることができます。細かく区切られた空間同士の結びつきが、全体として鑑賞に良いリズム感を与えてくれているのです。こうして、空間の個性と展示内容とが深く結びつくことによって、三菱一号館美術館でしか見ることのできない展覧会が生み出されます。
さて、展覧会の後には、おしゃれで楽しい三菱一号館美術館のミュージアムショップがおススメですが、ショップにはどういった工夫がなされているのでしょうか?
「それぞれの商品がストーリー、つまり物語を語れる商品を集めています」
石神さん
「当館のミュージアムショップにはコンセプトがありまして、それぞれの商品がストーリー、つまり物語を語れる商品を集めるという事になっています。1個1個の商品に何か付随した色々な、これ実はこういう経緯があって作られたものなんですよ。という、説明があるんです。」

写真4:地球儀紙風船 |
三菱一号館美術館のミュージアムショップでは、小さな可愛らしい消しゴムから、豪華なアクセサリーまで幅広い商品が揃っています。それもそのはず、アートグッズやデザイングッズに限らずに、「物語(ストーリー)」をコンセプトに、世界中から商品をセレクトしているからこそ。
紙風船を入れ込んだメッセージカード(写真4)は開館からの売れ筋の商品だそうで、新潟の海岸沿いの漁村で漁師やその妻たちが冬場の収入源として内職で作っていたというストーリーのあるもの。明治時代から作られ続けてきたという、こんな素敵なメッセージカードで手紙を貰ったらなんだか嬉しくなってしまいますね。
展覧会を見なくても入る事が出来るショップとあって、近隣のビジネスマンの間でもちょっとした手土産として商品が買われているそうです。まさに都市型ミュージアム、丸の内のオフィス街と融合しているんですね。
ところで三菱一号館美術館のカフェは、いつ来てもにぎわっていますが、その秘密は一体何でしょうか。
「どの時間帯に訪れても展覧会の余韻を感じる事が出来る Café 1894」

写真5:Café 1894 |
Café 1894に入ってまず驚くのが、高い天井に立派な柱。実は、8メートルの高さがあります。写真を元に明治時代の銀行営業室を忠実に再現したというクラシカルな雰囲気の中、優雅に飲食が楽しめるというのは嬉しいですね。展覧会特別メニューも充実しており、予約が必要なディナーをはじめ、ランチやデザートなどバラエティー豊かなメニューがそろっており、どの時間帯に訪れても展覧会の余韻を感じられるようにという心遣いがあります。
また、展覧会を訪れたお客様以外の丸の内ビジネスマンやOLたちなど、仕事帰りにふらりと寄ってお酒を楽しんだり、デートにも利用されたりと、幅広い層から好評を得ているそうです。夜メニューの一つ、「一号館プチ飲みスペシャル(1500円)」は、なんと美術館職員から企画を募り実現したメニューとのことで、展覧会からショップ、カフェと、トータルで楽しんでもらおうという心意気を感じられます。
ここでしか出来ない魅力ある展示から、ミュージアムショップやカフェまで、クラシカルな建物を存分に活用した三菱一号館美術館では、展覧会を見に来た人もそうではない人も、ここを利用し、楽しんでもらいたいという思いに溢れていました。鬼柳さん、安井さん、石神さん、酒井さん、後藤さん、ありがとうございました。(2011年11月18日、浜崎・高橋取材)
- 三菱一号館美術館
- 住所:東京都千代田区丸の内2-6-2
- TEL:03-5777-8600(ハローダイヤル)
- URL:http://www.mimt.jp/
- 「岐阜県美術館所蔵 ルドンとその周辺―夢見る世紀末」展
- 三菱一号館美術館《グラン・ブーケ(大きな花束)》収蔵記念
- 2012年1月17日(火)~3月4日(日)まで